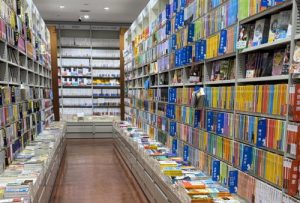今年の夏は記録的な猛暑続きで、まだまだ残暑も厳しい日が続いていますが、朝夕は心なしか風が心地よく感じられる日が増えたような気がします。
今年の夏も、季節は秋へと着実に移り変わってきているのではないのでしょうか。

秋と言えば、風物詩の一つとして、「中秋の名月」があります。
中秋の名月は、単に満月を指すのではありません。
旧暦では7月から9月が秋とされており、そのちょうど真ん中の月である8月の満月を「中秋の名月」と呼ぶようになりました。
旧暦8月15日の夜に見える月のことで、今年は10月6日(月)にあたります。
中秋の名月は、もともと中国から伝わった「中秋節(ちゅうしゅうせつ)」という行事に由来し、平安時代に日本に伝わりました。
日本では、稲の実りに感謝する「収穫祭」の意味合いが加わり、月を眺めながら秋の恵みに感謝する風習として定着しました。
この夜に見られる満月は、一年のうちで最も美しいとされ、昔から多くの人々に親しまれてきました。

この行事には「月見団子」や「ススキ」を供える習慣があります。
丸い月見団子は、豊かな実りと健康を願う象徴であり、ススキは稲穂の代わりに用いられ、魔除けの意味もあるといわれています。
これらを供えながら、静かに夜空を見上げることで、自然の美しさと季節の移ろいを感じることができるのではないのでしょうか。

現代では忙しい日常のなか、ゆっくり月を眺める機会が少なくなっていますが、たまには仕事の手を休めて、家族や仲間と一緒に秋の夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。
心穏やかなひとときを過ごすことができるかもしれません。
福山支店 井上 宜幸